パニック特有の症状「予期不安」との付き合い方について、panicoの考えをまとめました。
- 予期不安を無くしたいと意識しすぎると、かえって無くならない
- 不安は無くすのではなく、自分の中に居させてあげる
不安の無限ループ
予期不安、無くしたいのに無くならない!
予期不安とは
・「またパニック発作が起きたらどうしよう」「次はもっと激しいのではないか」と
不安になること。
・発作が起きていないのに、発作が起きる可能性に対して不安になり、
その状況(電車や人混みなど)を回避するようになる。
パニックにはつきものの「予期不安」。
いちどパニック症状を経験すると、
「怖かった、苦しかった。もう2度とあんな状態になりたくない!」と思うのは当然のこと。
panicoも、またパニックに陥らないように、
同じ状況を避けたり、お薬を飲んで乗り切りながら、
どうしたらこの不安を無くせるんだろう、
どうしたら発症前の呑気に生きてた頃のようにに戻れるんだろうと、
色々と考えて考えて・・・考えるほど不安になる、の繰り返しでした。
このループは失恋に似ていて、
好きだった人を忘れたいのに、忘れたいと思えば思うほど、
かえってその人のことを思い出してしまって、忘れられないのよね。
心理学の有名な実験「シロクマ実験」

じゃあ意識すればするほど、忘れられなくなるのはどうしででしょう?
ここで心理学の有名な実験を、読者のみなさんに体験してもらおうと思います。
「今から30秒間、シロクマのことを絶っっ対に考えないでください!」
では、スタート! (30秒数えましょう)
・・・・いかがでしたか?
たいていの方は、
「え?急にシロクマ!?は?意味わかんないんだけど?(シロクマが頭から離れない)」
「よし、わかった。シロクマのことは考えない、考えない・・・って逆に考えとるやないかい!」
「別のことを考えればいいんだよね、えっと、今食べたいものはお寿司かな・・・。うん、シロクマのことは考えないでいられた!・・・しまった、思い出してもうた!」
というように、シロクマがかえって頭から離れない。シロクマのワードだけにとどまらず、
北極の氷を背景にした真っ白なシロクマの姿が鮮明に目に浮かんで離れない!
「考えてしまった」というみなさん、大丈夫です。
これは、人間に備わった脳の働きであって、仕方のないことなんです。
🐻 シロクマ実験とは 🐻
シロクマ実験は、アメリカの心理学者ダニエル・ウェグナーが1987年に提唱した
「皮肉過程理論」を説明するために行われた心理学の実験です。
この実験は、「何かを考えないように意識すればするほど、かえってそのことが頭から離れなくなる」という現象(思考の抑制によるリバウンド効果)を示すものです。
実験では、参加者を3つのグループに分け、シロクマの映像を見せました。
Aグループ: シロクマのことを覚えておくように指示。
Bグループ: シロクマのことを考えても、考えなくてもよいと指示。
Cグループ: シロクマのことだけは絶対に考えないように指示。
一定時間が経過した後、実験協力者に映像についてどれだけ覚えているかを尋ねたところ、
「絶対に考えないでください」と指示されたCグループが、
最も映像について詳しく覚えていたという結果が出ました。
特定の思考を抑制しようとすると、かえってその思考が頻繁に現れてしまう「リバウンド効果」が起こります。
人間は思考をコントロールしようとするとき、「実行過程」と「監視過程」という2つのプロセスが働きます。
- 実行過程: 実際に思考を行うプロセスです。
- 監視過程: 自分の思考が、コントロールしたい内容に反していないかを監視するプロセスです。例えば、「シロクマを考えない」という指示を守るために、脳は常に「シロクマ」を覚えておく必要があります。このため、かえってシロクマのことが頭から離れなくなるのです。
不安を無くすのではなく 居させてあげる
症状が出なくなっても、不安は尽きない
panicoはかれこれ4年間はパニック発作を起こしていませんが、
また発作を起こすかもしれない不安はずっとあります。
この不安がある限り、また症状が出る可能性もあり続けるのだから、
できれば不安も、症状が出たときの記憶さえも、無くしてしまえたら、と何度も思いました。
でも、シロクマ実験からわかる通り、
無くしたいと思えば思うほど、不安は減るどころか増えていく。
どう頑張っても、また症状が出るかもしれない不安は尽きることはないし、
あんなに怖い体験をしたのだから簡単に忘れることはできないし、
同じような場面を避けたいのは当然のことだし、
不安ってそもそも誰にでもあるもの。
とりわけ私は不安に対して昔から敏感だから、パニック症になったのだと思う。
私は、不安と戦うんじゃなくて、仲良くしなきゃいけないんだ。
だったら作戦変更して、不安が自分の中に居ることを許可してやろう。
そう思い始めました。
『不安さんたち、居てもいいよ。でもそれ以上成長しないでね!!』
今以上に大きくならないように監視もしてケアもして、
長期的にすみっこのほうに追いやっていくような計画で、
不安を自分の中に居させてあげることにしました。

サンエックス すみっコぐらし ぬいぐるみS ほこり MY92801
不安を受け入れることで、ラクになった!
不安を受け入れ共存していくよう切り替えたあとは、
心身ともにだいぶラクになりました。
panicoは不安に対して以下のマネジメントを心がけています。
不安のマネジメント
・これ以上大きくならないように日頃から心身のケアをする。
・また大きくなってきたら、早めに気づいて対処する。
・症状が出てしまったときの対処法をいくつか考えておく。
そして、余裕のあるときに対処法を練習しておく。
(電車の中だったら〇〇、運転中だったら〇〇・・・など)
不安のマネジメントは、防災訓練と似ているな・・・とこれを書いていて思いました。
『憎き不安も、愛すべき自分の中の一面。仕方ない、居させてあげよう!』
と腹をくくったのでした。

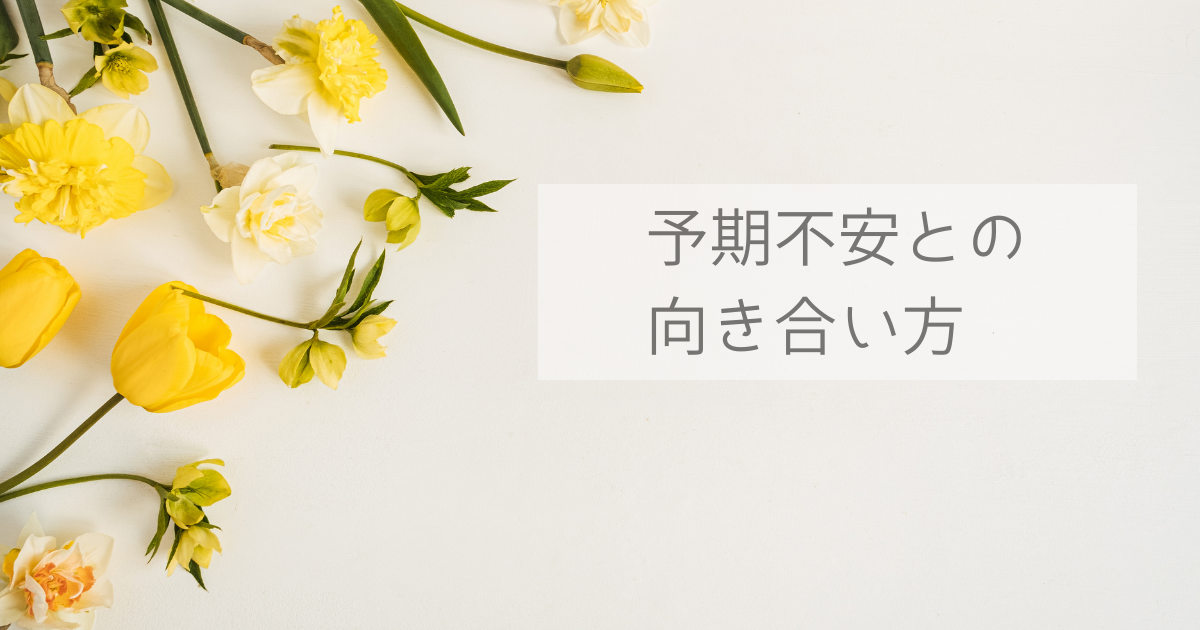


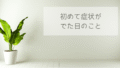
コメント